「今年もか」と残念に思った。なくなって欲しいと心から願った。夏の甲子園大会。両校の攻防がピークを迎えた時に観客が行う「タオル回し」である。あれ、やめませんか。
8月19日の3回戦、仙台育英対大阪桐蔭でも起きた。0―1と仙台育英が1点ビハインドで迎えた9回裏2死満塁。直前の2死一、二塁では遊ゴロでゲームセットと思われたが、大阪桐蔭の一塁手がベースを踏み損ない、チャンスが拡大していた。勝負所なのは分かるし、興奮するのも分かる。それでも観衆がタオルを回し、守備側のチームにプレッシャーをかけることには、強烈な違和感を覚える。
去年の夏もそうだった。甲子園の2回戦、東邦対八戸学院光星だ。東邦が9回裏、4点差を追いつき、なおも2死二塁でサヨナラ打を放ち、最大7点差をひっくり返すミラクル劇を成し遂げた。あの時、ネット裏に座ったドリームシートの子供たちから外野席まで、応援歌に合わせて球場全体がタオルを振り回し、東邦ナインを後押しした。
あらかじめ記すが、先日の仙台育英ナインやこの時の東邦ナインの最後まで諦めない心は、すごいと思う。立派なもので、称賛に値する。それとは全く別に、観衆が勝敗の行方に土足で介入しようとすることには、やはり反対だ。
昨夏の八戸学院光星の投手は試合後、“完全アウェー”の雰囲気に「全体が敵なのかなと思いました」と言った。本音だろう。夢舞台に憧れ、頑張ってそのマウンドに立てた球児に、そう思わせる甲子園大会であって欲しくない。
プロ野球ならばいいと思う。観衆はスタジアムで、思いのままに楽しむ権利を有する。打者は打てなきゃヤジられ、投手は打たれりゃブーイングを浴びる。称賛や非難をたっぷり背負う代わりに、プロ野球選手には高額の年俸が支払われる。ホームとアウェーで雰囲気や風景が大きく変わるのも醍醐味だ。でも、高校球児はアマチュアである。甲子園に見に行く人は応援する学校だけでなく、対戦するチームにも「頑張れ」の思いを胸に、グラウンドを見つめられないものだろうか。
背景には甲子園大会の「フェス化」があると思う。見るだけでなく、参加する。感想を投稿し、ファン同士で共感し合ったりする。それはいいことだと思う。大きな声で応援するのは素晴らしいことだけれど、「語り継がれる伝説」の証人になることを望んだ結果、プレーヤーに恐怖を与えるのはやり過ぎだし、マナー違反だ。
「タオル回し」はする方に悪気はなくても、守る選手側にとってはプレー上の障害でしかない。大会本部は出場校にこの行為の自粛を求めている。理想は来場者に禁止するのではなく、観衆が「高校球児が嫌がることはやめようよ」と自発的に考え、自然になくなることだ。
高校球児は礼に始まり、礼に終わる。応援団やブラバンもエール交換を行う。お互いがリスペクトし合い、全力を尽くす高校野球の世界に、「タオル回し」はそぐわない。
|
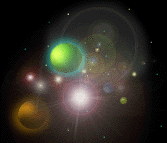

 ©1996-2025 不思議研究所 All rights reserved.
©1996-2025 不思議研究所 All rights reserved.